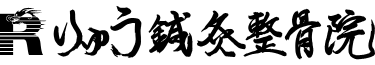スタッフブログ 新着一覧
-
小顔になりたい方へ! こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
小顔になりたいけど、マッサージやエステだけじゃ効果を感じにくい…そんな風に感じていませんか?
そんな方にこそ、ぜひ知ってほしいのが 美容鍼(びようばり)。
実は、顔のむくみやたるみ、フェイスラインのゆるみには「内側からのケア」がとても大切なんです。
今回は、美容鍼が小顔に効果的な理由や、その魅力について分かりやすくご紹介します!
美容鍼ってなに?
美容鍼は、顔の筋肉やツボに**極細の鍼(はり)**を刺して、血行やリンパの流れを促進する東洋医学に基づいた美容法です。
「顔に鍼って痛くないの?」と心配な方も多いですが、使うのは髪の毛より細い鍼なので、痛みはほとんどありません。
リラックスしながら受けられるのが特徴です。
小顔に効く!美容鍼の3つの理由
1,むくみ改善でフェイスラインがスッキリ
顔のむくみは、リンパや血流の滞りが原因。
美容鍼はツボや筋肉に直接アプローチして流れを良くし、その場でスッキリ感を実感する方も多いです。
2,筋肉のゆるみ・コリにアプローチ
パソコンやスマホの長時間使用で、表情筋は意外とコリやすくなっています。
美容鍼は深層の筋肉にもアプローチできるので、たるんだフェイスラインを引き締めるサポートになります。
3,自然治癒力を高め、肌の弾力アップ
鍼を刺すことでお肌の内側に微細な刺激を与え、コラーゲン生成をサポート。
ハリ感が増し、結果的に顔全体が引き締まって見えるようになります。
美容鍼はどれくらいで効果を感じる?
初回でも「フェイスラインが上がった」「目元がスッキリした」と感じる方が多いですが、継続することでより効果が定着します。
目安は、
最初の1ヶ月は週1回
その後は2~3週に1回のメンテナンス
個人差があるので、担当の鍼灸師さんと相談しながら進めるのがベストです。
まとめ|小顔になりたいなら「表面+内側」からのケアを
小顔になりたいなら、マッサージやスキンケアだけでなく、内側からのアプローチが鍵。
美容鍼は、むくみ・たるみ・コリを根本からケアできるからこそ、多くの美容意識の高い方に選ばれています。
「最近顔が大きく見える…」「写真写りが気になる」
そんな方は、ぜひ一度美容鍼を体験してみてください! -
睡眠の質について こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
「ちゃんと寝たはずなのに、なんだか疲れが取れない…」
そんなふうに感じたことはありませんか?
睡眠は、ただ長くとれば良いというものではありません。
実は“質の高い睡眠”こそが、心と体の健康を支えるカギなのです。
この記事では、睡眠の質の重要性と、それを高めるための具体的な方法についてお話しします。
1. 睡眠の「質」とは?
まず、「睡眠の質」とは何かを簡単に説明します。
質の高い睡眠とは、
・寝つきが良い
・夜中に目が覚めない
・朝すっきり目覚める
・日中に眠気が少ない
といった状態を指します。
ただ「8時間寝た」からといって良い睡眠とは限らず、浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)がバランスよく取れているかが大切なのです。
2. 睡眠の質が悪いとどうなる?
睡眠の質が悪くなると、以下のような影響が出てきます。
・集中力・記憶力の低下
・感情のコントロールが難しくなる(イライラ、うつっぽさ)
・免疫力の低下
・肌荒れ・太りやすくなる
・生活習慣病のリスク増加(高血圧、糖尿病など)
つまり、睡眠の質が悪いと、見た目からメンタル、さらには寿命にまで影響を及ぼす可能性があるのです。
3. 質の高い睡眠をとるためのポイント
では、どうすれば睡眠の質を高めることができるのでしょうか?今日からできるシンプルな習慣をいくつかご紹介します。
・就寝前のスマホ・PCは控える
ブルーライトは脳を覚醒させ、寝つきを悪くします。寝る1時間前からは画面を見ないようにしましょう。
・毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
体内時計を整えることで、自然と眠気が来るようになります。
・寝る前のリラックスタイムを作る
読書、ストレッチ、深呼吸など、心を落ち着ける時間を持ちましょう。
・カフェイン・アルコールに注意
特に夕方以降のカフェインは眠りを妨げることがあります。アルコールも寝つきは良くなっても睡眠の質を下げてしまいます。 -
肩こりの原因! こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
毎日の生活の中で、ふと感じる「肩が重い…」「首まで痛くなってきた…」という不快感。それ、肩こりかもしれません。
現代人の多くが抱えるこの症状、一体なぜ起きるのでしょうか?
今回は、肩こりの主な原因を分かりやすくご紹介します。
肩こりってどうして起こるの?
肩こりは、肩や首周辺の筋肉が緊張し、血流が悪くなることで疲労物質がたまり、痛みや重だるさを感じる状態です。では、その筋肉の緊張はなぜ起こるのでしょうか?
原因①:長時間の同じ姿勢
パソコン作業、スマホの操作、車の運転など、長時間同じ姿勢をとることは、肩こりの大きな原因です。特に、前かがみになるような姿勢は首・肩に負担がかかります。
対策:
・1時間に1回は立ち上がってストレッチをする
・デスクワーク時の椅子やモニターの高さを見直す
原因②:運動不足
運動不足は筋力の低下や血行不良を引き起こし、肩こりを悪化させる要因になります。筋肉をあまり使わないと、疲労物質が流れにくくなるのです。
対策:
・ウォーキングや軽いストレッチを毎日続ける
・肩甲骨まわりを意識的に動かす運動を取り入れる
原因③:ストレス・精神的緊張
ストレスを感じると、無意識に肩に力が入り、筋肉がこわばります。これが続くと慢性的な肩こりに発展することも。
対策:
・深呼吸や瞑想などリラックスできる時間を持つ
・睡眠をしっかりとることも効果的
原因④:目の疲れ(眼精疲労)
パソコンやスマホの画面を長時間見ることで目の筋肉が疲れ、それが首・肩の緊張につながることがあります。
対策:
・1時間に1回は画面から目を離し、遠くを見る
・目を温めるアイマスクなどもおすすめ
原因⑤:冷え
意外と見落とされがちなのが「冷え」です。冷房の効いた部屋で長時間過ごすことで筋肉が冷え、血流が悪化して肩こりを引き起こします。
対策:
・肩や首を冷やさないよう、上着やストールを活用
・湯船にゆっくり浸かって体を温める
肩こりは生活習慣のサイン
肩こりは一時的な不快感ではなく、生活習慣の乱れや身体の不調のサインでもあります。無理に我慢せず、早めにケアをしてあげることが大切です。
あなたの肩こりは、どの原因に当てはまりそうですか?
まずは日常生活を少し見直して、できることから始めてみましょう! -
自律神経について こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
最近「なんとなく疲れが取れない」「気分が落ち込みやすい」と感じていませんか?
もしかすると、それは 自律神経の乱れ が原因かもしれません。
今回は、私たちの健康に深く関わる「自律神経」について、基本的な知識から整えるための方法、そして整体・鍼治療がなぜ効果的なのかまで、わかりやすく解説していきます。
◆ 自律神経とは?
自律神経とは、自分の意思ではコントロールできない身体の働きを自動で調整してくれる神経のことです。
たとえば、呼吸・心拍・体温・血圧・消化など、私たちが意識せずに行っている生命活動を支えています。
自律神経には主に以下の2つがあります。
・交感神経:活動・緊張・ストレスに関係(昼モード)
・副交感神経:休息・リラックス・回復に関係(夜モード)
この2つの神経がバランスよく働くことで、私たちは健康でいられるのです。
◆ 自律神経が乱れるとどうなる?
自律神経のバランスが崩れると、さまざまな不調が現れます。代表的なものは以下の通りです。
・慢性的な疲労感
・頭痛・めまい
・睡眠障害(眠れない、途中で起きる)
・消化不良や胃の不快感
・動悸・息切れ
・イライラ・不安感・集中力の低下
・手足の冷えやほてり
原因は、ストレス・不規則な生活・睡眠不足・運動不足・季節の変わり目など、多岐にわたります。
◆ 自律神経を整える5つの方法
1. 生活リズムを整える
毎日同じ時間に起きて、同じ時間に寝る習慣をつけましょう。朝日を浴びることで、体内時計がリセットされます。
2. 深呼吸・瞑想
ゆっくりと深い呼吸をすることで、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。
3. 適度な運動
ウォーキングやストレッチ、ヨガなど軽い運動は自律神経を整える効果があります。
4. お風呂でリラックス
38~40度くらいのぬるめのお湯に15分ほど浸かると、副交感神経が活性化され、心も体も緩みます。
5. スマホ・PCの使いすぎに注意
ブルーライトは交感神経を刺激します。就寝1時間前からはなるべくデジタル機器を避け、心を落ち着かせましょう。
◆ 整体や鍼治療も効果的!
近年、自律神経の乱れによる不調に対して、整体や鍼(はり)治療が注目されています。
◎ 整体の効果
整体では、骨格や筋肉のバランスを整えることで、神経や血流の流れを改善します。
特に首や背骨まわりの筋肉が緊張していると、自律神経がうまく働かなくなることがあります。
整体で緊張をゆるめ、体の歪みを調整することで、副交感神経が優位になり、自然とリラックスできる状態になります。
◎ 鍼治療の効果
鍼治療は、東洋医学の観点から「気(エネルギー)」や「血(けつ)」の流れを整える方法です。
経絡(けいらく)と呼ばれるエネルギーの通り道に鍼を打つことで、自律神経のバランスを調整し、内臓の働きや睡眠、精神状態の安定に効果が期待できます。
実際に、不眠・不安・頭痛・胃の不調などで鍼灸治療を受けて改善したという声も多くあります。
※整体・鍼治療は、国家資格を持った施術者のもとで受けることが安心・安全です。 -
腱鞘炎について こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
今回は、手や指が痛くなる「腱鞘炎(けんしょうえん)」について、原因や症状、日常でできる対策まで、分かりやすく解説していきます。
腱鞘炎ってどんな病気?
腱鞘炎とは、筋肉と骨をつないでいる「腱(けん)」と、それを包んでいる「腱鞘(けんしょう)」が炎症を起こす状態のことをいいます。特に、手首や指をよく使う人に起こりやすいのが特徴です。
腱鞘炎の主な原因
腱鞘炎は、使いすぎ(オーバーユース)が大きな原因です。たとえば…
・パソコンやスマホの長時間使用
・子育てでの抱っこやお世話
・ピアノ、ギターなどの楽器演奏
・スポーツや家事での繰り返し動作
これらが続くと、腱と腱鞘がこすれ合って炎症を起こし、痛みや腫れが出てきます。
どんな症状が出るの?
・手首や親指の付け根がズキズキ痛む
・指や手を動かすと引っかかる感じがする
・腫れて熱っぽく感じる
・朝起きたときにこわばりを感じる
特に有名なのが「ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)」という腱鞘炎の一種で、親指の腱が炎症を起こします。
腱鞘炎の対策・治し方
・安静にする
とにかく使いすぎないことが大事!
サポーターやテーピングで固定すると楽になります。
・冷やす・温める
痛みが強いときは冷やす、慢性的な場合は温めると血行が良くなります。
・ストレッチやマッサージ
無理のない範囲で筋肉をほぐしてあげましょう。
・病院に行く
我慢せず、整形外科や整骨院で診てもらうことも大切。
状態によっては注射や手術が必要なこともあります。
・鍼灸治療
鍼灸治療でツボや筋肉の緊張している部分を刺激することで、以下のような効果が期待できます。
:炎症部分の血流改善
:痛みを抑える神経の働きを調整
:手首や腕の筋肉の緊張緩和
:自然治癒力の促進
予防のポイント
・長時間同じ動作を続けない
・パソコンやスマホの姿勢を見直す
・こまめなストレッチを習慣に
・手を冷やさないようにする(特に冬場)
まとめ
腱鞘炎は「ちょっとした手の痛み」から始まりますが、放っておくと日常生活にも支障が出てしまいます。
早めの対策と予防で、手や指をいたわってあげましょう。
もし気になる症状がある方は、無理せず医療機関に相談してください。 -
巻き肩の原因と対策! こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
今回は、多くの方が悩まされている「巻き肩」についてお話しします。
デスクワークやスマホの長時間使用が当たり前になっている現代では、気づかないうちに姿勢が崩れて「巻き肩」になっている方が非常に多いです。
肩こりや頭痛、猫背、さらには呼吸の浅さにもつながる厄介な「巻き肩」。
今回は、
・巻き肩が起こる原因
・放っておくとどうなる?
・プロによる施術アプローチ
・自宅でできるセルフケア方法
をご紹介します。
巻き肩とは?
巻き肩とは、肩が身体の前方に巻き込むように出てしまっている状態のことです。
横から見たときに、本来なら耳のラインにあるはずの肩が、前にズレてしまっているのが特徴です。
1. 長時間の猫背姿勢(デスクワークやスマホ操作)
パソコン作業やスマートフォンの操作などで前傾姿勢が続くと、胸の筋肉(大胸筋や小胸筋)が縮み、背中の筋肉(僧帽筋・菱形筋など)が引っ張られてバランスが崩れます。
2. 筋力バランスの崩れ
胸の前の筋肉が強く、背中側の筋肉が弱くなると、肩が前方に引っ張られやすくなります。
3. 呼吸の浅さ
浅い呼吸を繰り返すと肋骨周辺の動きが悪くなり、胸郭の柔軟性が低下。結果として肩が内に入りやすくなります。
4. ストレスや緊張
緊張状態が続くと、自然と肩が上がり、巻き肩を助長する姿勢になってしまいます。
巻き肩を放っておくと?
・肩こり・首こり・背中のハリ
・呼吸が浅くなる
・猫背や姿勢の悪化
・頭痛や自律神経の乱れ
・見た目が老けて見える
巻き肩は「見た目の問題」だけでなく、身体のさまざまな不調の原因になります。
施術でのアプローチ
巻き肩の改善には、筋肉のアンバランスを整えることが重要です。
1. 筋膜リリース・ストレッチ
固まって縮んでしまった胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)をゆるめます。
2. 姿勢矯正・骨格調整
肩甲骨や背骨の動きを正常に戻すことで、肩が本来の位置に戻りやすくなります。
3. 呼吸改善の指導
深い呼吸を促すための横隔膜エクササイズなどを通じて、姿勢全体を改善します。
自宅でできるセルフケア
1. 壁ストレッチ(胸を開く)
・壁の前に立ち、腕をL字にして壁に当てます
・肩を壁につけたまま身体を反対側にひねる
・胸の前が伸びるのを感じながら30秒キープ
2. 肩甲骨はがしストレッチ
・両腕を背中の後ろで組む
・肩甲骨を寄せるように胸を開く
・10秒キープを3セット
3. タオル肩回し体操
・タオルを両手で持って、頭の上から背中の方へ回す
・肩の可動域を広げ、正しい位置に戻す練習になります
4. 呼吸法(腹式呼吸)
・鼻から息を吸い、お腹を膨らませる
・口からゆっくり息を吐く
・1日5分を目安に行うと胸郭の柔軟性が高まりやすくなります -
月経前症候群について こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
今回は多くの女性が毎月感じている「月経前症候群(PMS)」について、わかりやすくお話ししていきたいと思います。
月経前症候群(PMS)とは?
PMS(Premenstrual Syndrome)とは、生理(=月経)が始まる数日〜2週間ほど前から心や体にさまざまな不調が現れることをいいます。
「毎月この時期になるとイライラする…」「急に落ち込む」「肌荒れや腹痛がつらい」など、それぞれ症状は違いますが、決して気のせいではありません。
主な症状
PMSの症状は人それぞれですが、大きく分けて「心」と「体」の両方にあらわれます。
心の症状
・イライラする・怒りっぽくなる
・気分が落ち込む・涙もろくなる
・不安になる・集中力が低下する
・対人関係がつらく感じる
体の症状
・下腹部の痛みや張り
・胸の張りや痛み
・頭痛
・むくみ・体重増加
・眠気や不眠
・肌荒れ
PMSの原因は?
はっきりとした原因はまだ解明されていませんが、主に「ホルモンバランスの変化」が影響していると考えられています。
排卵後から月経に向けて、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンが急激に変動します。このバランスの崩れが、心と体に影響を与えているとされています。
どう対処すればいい?
PMSは一時的なものとはいえ、毎月繰り返すとなると本当にしんどいですよね。少しでもラクになる方法をご紹介します。
1. 自分の周期を知る
まずは、自分の生理周期や症状をアプリや手帳に記録してみましょう。「あ、またこの時期だな」とわかるだけでも心構えができます。
2. 食事と生活習慣を見直す
塩分やカフェインを控える
ビタミンB6・カルシウム・マグネシウムを摂る
適度な運動やストレッチで血流改善
3. リラックスを心がける
アロマや温かいお風呂でリラックス
よく眠る
無理せず「今日はちょっと休もう」と思える環境づくり
4. つらいときは医師に相談を
生活改善だけではどうにもならないほど症状が重い場合は、「月経前不快気分障害(PMDD)」の可能性もあります。婦人科で相談すれば、漢方薬や低用量ピル、カウンセリングなどの選択肢があります。
PMSは「甘え」でも「気のせい」でもありません。心と体が出しているSOSです。周りの人に理解してもらうことも大切ですし、自分自身も無理しないで過ごすことが大事です。
毎月を少しでも穏やかに過ごせるように、自分にやさしくしてあげてください。 -
筋肉痛について こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
今回は筋肉痛についてお話します。
「筋肉痛の原因・仕組み」
筋肉痛とは、運動によって生じる筋肉の痛みです。以前は、激しい運動をすると筋肉に疲労物質である乳酸がたまり、筋肉痛を引き起こすと考えられていました。しかし、乳酸はエネルギーとして再利用できることがわかり、現在では「乳酸は疲労物質ではない」と認識されています。そこで、新たに台頭してきたのが、運動による筋繊維の損傷を修復する際に、炎症が起こって痛みを引き起こすという説です。トレーニングなどで普段使わない筋肉を使ったり、同じ動作を繰り返したりすると、筋肉を構成している繊維(筋繊維)に細かな傷ができます。傷んだ箇所を修復する過程で炎症反応が生じて、ブラジキニンなどの痛みを生み出す刺激物質が生成され、筋肉痛が出現すると考えられています。
「筋肉痛の種類」
①即発性筋痛
急性筋肉痛とも呼ばれる、運動した直後や早ければ運動している最中に起こる筋肉痛です。激しい運動をして筋肉に強い負荷がかかり、過度の緊張状態が続くと、血の巡りが悪くなるため、筋肉の代謝物である「水素イオン」がたまりやすくなって筋肉痛が起こります。
②遅発性筋痛
運動して数時間から数日後に生じる筋肉痛。一般的に筋肉痛といわれるのは、この遅発性筋痛を指します。最も遅発性筋痛になりやすいのが、下り坂を駆け下りたり、重い荷物を下ろしたりするなど、筋肉を伸ばしながら力を発揮する伸張性(エキセントリック)運動です。
「年をとると筋肉痛が遅く出る」といわれますが、実は医学的には肯定も否定もできない通説。普段あまり運動をしない人は毛細血管が発達しておらず、筋繊維を修復したり、痛み物質を取り除いたりするのに時間がかかります。年齢を重ねるとからだを動かす機会が減りがちなので、年齢に関わらず適度な頻度で運動するよう心がけましょう。
運動直後のマッサージは効果的です。運動直後に張っている筋肉をほぐし、血行を促進させたり、溜まった老廃物や毒素を流し出す働きがあり、疲労感を残しにくくしてくれます。また筋肉痛に対する鍼灸治療は、筋肉の炎症や痛みを軽減し、回復を早める効果が期待できます。鍼灸による刺激は、脳内麻薬様物質(エンドルフィン)の分泌を促し、鎮痛効果をもたらすと考えられています。
気になった方はぜひ受けてみてください! -
外側上顆炎 外側上顆炎とは肘の外側にある外側上顆に炎症が起きる疾患です。テニス肘とも呼ばれています。
原因はテニスやゴルフなどのスポーツや、重いものを持ち上げたり、パソコン作業など手首を繰り返し使うことが考えられます。また加齢による腱の劣化も考えられます。
症状
物を持つ、タオルを絞る、ドアノブを回すなどの動作で肘の外側に痛みが出ます。
検査方法
トムゼンテスト
・肘を伸ばしたまま手首を曲げる様にして、抵抗をかけた状態で手首を伸ばしてもらいます。
チェアーテスト
・患者さんに肘を伸ばしたまま手で椅子持ち上げてもらいます。
中指伸展テスト
・中指を上から抑えるのに抵抗して、患者さんに肘を伸ばしたまま中指を伸ばしてもらいます。
予防方法は、前腕伸筋郡のストレッチや肘のサポーターや専用のバンドを使用して筋肉や関節を保護するのも有効です。 -
むくみに負けるな!!! こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
6月なのに真夏のような暑さが続いており 梅雨はどこいった⁉ 状態ですが、まだ梅雨は明けておりません!
梅雨の時期に起こりやすいのが『むくみ』朝起きたら顔がパンパン、夕方には足がむくんでるなんてことありませんか?
湿気とむくみは大きく関係しているんです!!
湿度が高くなると体内の水分代謝が滞りやすくなり余分な水分まで身体に溜まってしまうんです。さらにさらに!冷たい飲み物の摂りすぎ+エアコンなどによる冷え で血流やリンパの流れが悪くなり余計にむくみやすい体になってしまいます。
そこでご自身でできる!「むくみに関係するツボ」を紹介
*陰陵泉(いんりょうせん)
膝の内側、すねの骨をなぞって骨が終わる所のくぼみ
*足三里(あしさんり)
膝のお皿の外側から指4本分下、すねの骨の外側
*三陰交(さんいんこう)
内くるぶしの頂点から指4本分上、すねの骨の内側
*太谿(たいけい)
内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ
*湧泉(ゆうせん)
足の裏、土踏まずの少し上、足指を曲げたときにできるくぼみ
ツボ押しは”痛気持ちいい”位がベスト
ぜひやってみてくださいね!なにかあればお気軽にご相談ください。