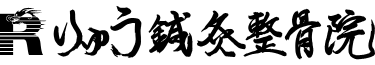スタッフブログ 新着一覧
-
首肩こりに鍼灸治療は効く? こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
今回は鍼灸治療は首肩こりに効くのかご説明致します!
結論、鍼灸治療は首肩こりに効きます!!
まず、首肩こりについてご説明致します。
首肩こりは、姿勢の悪さや極度の筋緊張(筋肉が常に収縮)などが原因で起こり、それに伴って痛みや張り感、だるさ、悪化すると頭痛や吐き気などを伴います。筋緊張が常に起こっていると、血流が悪くなり、老廃物が溜まり、痛みなどの症状が発症してしまいます。
次に鍼灸治療についてご説明致します。鍼灸治療は、血流の流れを良くしたり、筋緊張を緩和してくれたり、さまざまな効果があると研究でわかっています。
鍼灸治療によって軸索反射というものが体内で起こります。メカニズムは、
①鍼やお灸が皮膚表面、筋肉などに刺激を与える。
②神経組織である軸索が、鍼やお灸の刺激を中枢神経(脳や脊髄)に伝える。
③伝える際に、神経伝達物質(サブスタンスP、CGRPなど)が分泌される。
④神経伝達物質は、血行を促進する働きがある。
⑤血行が促進されることにより、痛み物質(ブラジキニンやヒスタミンなど)が排除され、痛みが緩和される。
というものです。
鍼やお灸で軸索反射が起こっているか判断するには、皮膚表面が赤くなっているかで判断できます。 これをフレア反応と言います。フレア反応は鍼灸治療をした箇所で起こり、毛細血管が拡張して血流が良くなっているので赤く反応がでます。
以上のことから、首肩こりに鍼灸治療が効くことがわかります!!
鍼灸治療をどのように行うか、基本的には首肩の筋肉の硬くなっている部分(硬結部)に行います。
鍼はとても細く丈夫なものを使用します。髪の毛ぐらいの細さで、注射針よりも10分の1のサイズなので痛みが少なく治療できます。また鍼管というものを用い、鍼がたわまないようにスムーズに刺すので痛みが少ないです。
お灸は主にせんねん灸というものを使用します。せんねん灸は別名を隔物灸といい、お灸と皮膚の間に台座があります。これにより温度を調節することができ、やけども起こらず安全に治療できます。
鍼灸治療は痛いイメージがありますが、現代の鍼灸治療はとても改良されており、痛みが少なく安全に治療を行えるようになっております。また国家資格を持っていないと日本では鍼灸治療ができないので、知識のある人が必ず治療を行うので安全に受けられます。首肩こりで悩んでいる方、興味のある方はぜひ受けてみてください! -
寝違え 朝起きたとき首や肩に痛みがあり動かせない。動かすと痛い。そんな経験ありませんか?
寝違えが起きる原因
・寝ているときの姿勢
寝返りが少ないと首に大きな負担がかかり、血行不良や筋肉疲労が起こってしまいます。そして、寝起きや寝返りといった急な動きによって硬くなった首の筋肉が損傷して、寝違えの痛みを生じる場合があります。
・睡眠時の環境
自分の身体にあってない寝具を使うと寝違えを起こしやすいと言われています。枕の高さが高すぎると血管が圧迫され血流が悪くなってしまいます。また柔らかすぎるマットレスを使用すると頭や背中の体重がかかる部分が沈み、首に余分な負担がかかり痛めてしまいます。
寝違えの対処方
寝違えを起こした直後の炎症期は冷やすことによって痛みの軽減、早期回復が期待できます。しかし冷やし過ぎると血行不良、筋緊張を起こしてしまうため10分~15分冷やして様子を見ましょう。痛みが落ち着いてきたら無理のない範囲で肩を動かしましょう。肩を動かすことによって血行が促進され痛みや可動域が改善されやすくなります。 -
この時期に咳が止まらない人にオススメのツボ こんにちは!りゅう整骨院です。
この時期になると体調を崩す方も多いと思います。
今回は症状別でオススメのツボをご紹介します。
≪風邪のひきはじめ≫
風門「ふうもん」
ツボの位置→うつむいた時、首のつけ根でいちばんでっぱっている骨のすぐ下のくぼみから骨2つ下がり左右外側にずれたところ
≪咳≫
天突「てんとつ」
ツボの位置→左右の鎖骨を結んだ中心にある少しくぼんだ部分
尺沢「しゃくたく」
ツボの位置→手のひらを上にした時の肘のシワの真ん中
≪熱≫
曲池「きょくち」
ツボの位置→肘を曲げたときにできる横シワの端、親指側にあるくぼみです。
ぜひ、セルフケアで押してみてください。 -
天気が悪い日にはお気を付けください こんにちは。りゅう鍼灸整骨院です
梅雨も近くなり足元が悪い日が続き足を滑らせ怪我をする人が増えて来るので今回は足首の怪我についてお話ししていきたいと思います。
足関節捻挫とは
足関節捻挫はスポーツ活動中や日常生活中の歩行時に、足関節を内側あるいは外側にひねることで起こります。ほとんどが内側によるもので前距腓靭帯損傷や外顆の裂離骨折を合併する場合があり注意する必要があります。
症状
足関節捻挫程度
・第Ⅰ度:前距腓靭帯損傷(捻挫)
・第Ⅱ度:前距腓靭帯損傷 踵腓靭帯損傷(部分断裂)
・第Ⅲ度:前距腓靭帯損傷 踵腓靭帯損傷 後距腓靭帯損傷(完全断裂)
接骨院で出来る治療
・初期の場合にはRACE処置を行う
・テーピングやサポーターなどを使い患部を保護する
・マッサージ
・ストレッチ
※ほとんどの場合は保存療法ですが一部手術が適応される場合があります
もしお困りの際はりゅう鍼灸整骨院までお気軽にご連絡ください。 -
ゴールデンウィーク明けの憂鬱対策!!! こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
待ちに待ったゴールデンウィーク!!皆さんは何をして過ごしていますか?実家に帰省したり、友達や家族と過ごしたり、おうちでゆっくりしたり、はたまたお仕事の日とも、、、
さて本題です。
連休中楽しんだ分、連休明けはなんだかカラダがだるーく、仕事が始まるのがおっくうになってしまう方!連休中に生活リズムが狂ってしまっているからかもしれません。そりゃゴールデンウィークくらいハメをを外していろいろしたいですよね...。しかし連日の遅寝遅起きで体内時計が狂ってしまったり、休日の過度なスケジュール、仕事へのストレスの蓄積が連休明けのだるさを連れてきている可能性があります!
そんな時は、
規則正しい生活を心がける。
体力に余裕の持ったスケジュールを。
栄養を摂取(疲労回復にはビタミンB群、ビタミンCが効果的!)
それでも辛い場合はりゅう鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。 -
目の疲れや疲労は東洋医学で治せる! こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
パソコンやスマホの使い過ぎ、読書や勉強で目が疲れたり、かすんだりしてませんか?
東洋医学では五臓六腑の内、肝がうまく機能していないと判断されます。
肝には疏泄作用と蔵血作用という2つの作用があります。
疏泄作用とは、体中に気(体を温め動かすエネルギー)を巡らせる作用です。情緒の活動をスムーズにしたり、消化吸収を滞りなく行ったりするのと関係があります。ストレス・怒り・緊張などで疏泄作用がうまくいかないと、肝は失調し、気が巡らなくなり、イライラ・落ち込み・情緒不安定・食欲不振・胃の痛み・動悸・手足の冷え・頭痛・めまい、目の症状などが現れます。
蔵血作用とは、血を貯蔵し、体の状態に合わせて血流をコントロールする作用です。心身の状態・運動量・環境に合わせて常に血の総量を調節しています。血の不足によって現れる症状は、めまい・ふらつき・髪や肌のパサつきなどです。また、血が不足すると肝を十分に機能させる血が確保できなくなるので、蔵血が十分に行われないだけでなく、肝の疏泄作用もうまくいかなくなります。
また肝は目、筋、爪と密接にかかわっています。
目→肝の働きが高ぶりすぎると目の充血が起こり、肝の蔵する血が不足すると、ドライアイや眼精疲労が起こります。
筋→肝の働きが高ぶりすぎると筋肉のけいれんや震えが起きます。また、肝の蔵する血が不足すると、筋が固くなる・引きつれたように痛む・運動機能が低下する・手足がしびれるといった症状を引き起こします。
爪→肝が血を十分に蔵していれば、爪は血色がよく、丈夫です。しかし、肝の蔵する血が不足すると、爪の血色は白く薄くなり、爪自体も薄く、割れたり反り返ったりします。
肝の作用を調節するには、酸味のある食べ物が有効です。パイナップルや柑橘系、オリーブやキウイなどが良いです。
目の症状は蔵血作用がうまく機能していないことが多いです。蔵血作用の機能を改善してくれる食べ物は、牛肉やレバー類、卵、マグロ、にんじん、枝豆などがあります。
食事で摂っても改善しない方はぜひ一度当院へいらしてください!その他のご相談も承っています! -
寝たきり生活 回避方法🤔 こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
人生100年時代。平均寿命が延び100年生きるのが当たり前になりつつありますね。
皆さん『平均寿命』ってご存知ですか?
→人が生まれてから死ぬまでの平均年数のこと。(男性:81.09、女性:87.14)
では、 『健康寿命』はご存知ですか?
→健康上の問題で日常生活制限されない年数のこと。(男性:47.57、女性:75.45)
男女それぞれ約9年、約12年の差があります。寿命が延びても健康寿命が長くないと不健康な期間が増え最悪の場合寝たきり生活になったり、医療費、介護費の負担も大きくなってしまいます。
元気に過ごすために健康寿命を延ばしこの差を縮める事が大切なのが分かりますね (´-ω-`)
そこで一つの目安が...
\\ロコモティブシンドローム(通称:ロコモ)//////
→骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で歩行や立ち座りなどの日常生活に障害をきたしている状態のこと。進行すると要介護や寝たきりのリスクが高くなります Σ(゚Д゚)
✔ ロコチェック ⚠一つでも当てはまったら注意⚠
☐片足立ちで靴下が履けない
☐家の中でつまずいたり滑ったりする
☐階段を上がるのに手すりが必要
☐家のやや重い仕事が困難になる
☐2キロほどの買い物をして持ち帰るのが困難
☐15分くらい続けて歩くことができない
☐横断歩道を青信号で渡り切れない
骨密度や筋肉量は40歳で低下し、50歳から急激に低下してしまうんです。
そ・こ・で
日常生活に『プラス・テン』を取り入れてロコモを予防していきましょう。
「プラス・テン」これは普段の生活に「+10分」身体を動かしましょうという意味で、1日に最低でも成人では60分、高齢者では40分カラダを動かすことが推奨されています。
車移動を自転車や徒歩に変えてみたり、最寄り駅の一つ手前で降りて歩いたり、30分に1回椅子から立ち上がってストレッチしてみたり...無理はせずにできることから続けることが大切ですね。
カラダを使ったらメンテナンスも大事です。何かあればご相談下さい。 -
健康とダイエットをサポートしてくれる?耳つぼジュエリーって? こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
最近、若い人たちに流行っている耳つぼジュエリーってご存知ですか?
耳つぼジュエリーとは、耳にあるつぼを刺激して健康やダイエットのサポートをする治療法です。
耳つぼが発見されたのは、1951年、フランスの医者であるポール・ノジェDrが発見しました。ポール・ノジェDrが完成させた理論とは、「耳には、身体のどの部分にも対応しているツボがあり、その耳のツボに針・焼灼・マッサージ・ 赤外線などで刺激を与えることで、治療効果が現れる。」というものでした。
1990年にはWHO(世界保健機関)にも認められ、世界に急速に普及されました。
耳つぼ療法は、耳介療法や耳鍼、オリキュロセラピーとも呼ばれており、フランスでは非常に厳しい法律のもとで、医師などの医療に携わる専門家だけが行うことのできる医療行為として認められています。
耳つぼの効果は、
・痛みの緩和(頭痛、肩こり、腰痛など)
・自律神経の乱れによる症状(不眠、ストレス、めまいなど)
・消化器系の不調(便秘、下痢、食欲不振など)
・婦人科系の症状(生理痛、更年期障害など)
・アレルギー症状の緩和
・ダイエットの補助
・禁煙の支援
など様々な効果があります。
耳つぼジュエリーは誰でも簡単に貼り付けられます。小さいビーズ玉みたいなものを貼り付けるのだけなので、とても安全です。またデザインが可愛く、キャラクターの物もあるので、おしゃれをして健康のサポートをしてくれるので、とてもおすすめです。
その他の施術をご希望の方やお悩みごとがありましたら、いつでも当院へいらしてください。 -
これただの睡眠不足じゃないかも… こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です。
人間切っても切れない関係にあるのは睡眠じゃないかなと思います。
今回睡眠の症状を大きく4つに分けて説明していきたいと思います。
〇入眠困難(寝たいのになかなか眠れない…)
一般的に布団に入ってから寝付くまでに30分以上かかってしまうもの。
(眠りにつく時間は年齢などによって個人差があるので本来の入眠時間と比べてどのくらい長くなっているのかが重要になります。)
・睡眠環境、生活習慣の変化、身体・精神的な問題など。不眠症の中で最も多いと言われています。
〇中途覚醒(夜中よく目が覚めるなぁ)
一度寝入ったものの夜間に何度も目が覚めてしまうもの。その後、なかなか寝付けないもの。
・精神的な問題、アルコール摂取、睡眠時無呼吸症候群、加齢など。日本人の成人の不眠の中で最も多いと言われています。
〇早期覚醒(あと2時間寝れるじゃん…)
起きる時間より2時間以上早く目が覚めてしまい、その後再入眠が出来ないもの。
・精神的な問題、アルコール摂取、加齢、更年期障害など。
〇熟眠障害(ちゃんと寝てるのに日中あくび止まらない…)
睡眠時間は十分とれているものの眠りが浅く、熟眠感が得られず日中に眠気を感じるもの。
・睡眠環境、睡眠無呼吸症候群など。熟眠障害は他のタイプの不眠症に伴うことも。
~セルフケアで出来る事~
・寝床は寝るためだけに使うこと
・寝る前は刺激物を避けること
→就寝時のカフェイン、アルコール、喫煙、明るすぎる照明などは眠りの妨げになります。
・毎日同じ時間に起きること
→体内リズムを整えます
・朝起きたら日の光を浴びること
・ストレスを溜めないこと
→気分転換することも大切です。
このようなことに気をつけてみて生活してみてくださいね! -
新生活スタートの季節!【春と自律神経の乱れの関係】 こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
4月は新生活が始まる季節ですね。新しい環境によって普段と違う環境になかなか慣れずストレスを受けやすい事、そして春は寒暖差が1番大きい季節でもあるため自律神経が乱れやすいんです。
*身体的症状
頭痛、めまい、立ちくらみ、動悸、腹痛、など
*精神的症状
不安、うつ、不眠、倦怠感、イライラする、など
こんな症状がある方はもしかしたら自律神経が乱れてるサインかも⁉
自律神経を整えるには『生活リズムを整えること』が大事なんです!
・朝起きたら朝日を浴びる
・朝ご飯を抜かない
・ストレッチをする
・湯船に浸かってリラックス
・寝る前にスマホを見ない などなど
意外とできてないものもあるのではないでしょうか?
このセルフケアに加えて当院では鍼灸治療や矯正などを用いて症状の改善をサポートさせて頂きます!
何かありましたらご相談ください!