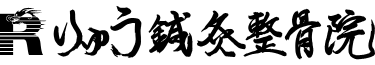スタッフブログ 新着一覧
-
小顔矯正について! こんにちは!
りゅう鍼灸整骨院です!
本日は小顔矯正についてお話ししていこうと思います!
小顔矯正とは、顔の輪郭やサイズを小さく見せることを目的とした美容法の一つです。主に顔の骨格や筋肉、リンパの流れに働きかけることで、顔のむくみやたるみを改善し、顔全体を引き締める効果を狙います。
一般的に、小顔矯正は以下のような方法で行われます:
1. マッサージ: 顔のリンパの流れを良くし、むくみを解消するためのマッサージが行われます。顔や首の筋肉をほぐすことで、血行促進やリフトアップ効果が期待されます。
2. 整体や骨格矯正: 頭蓋骨や顔の骨格のバランスを整えることで、顔の歪みを改善し、小顔効果を目指します。
3. 美容鍼: 鍼を使って顔の筋肉を刺激し、リフトアップ効果を高める方法です。コラーゲンの生成を促進し、肌のハリを向上させることが期待されます。
4. フェイシャルエクササイズ: 特定の顔の筋肉を鍛えるためのエクササイズが推奨されることもあります。これにより、顔の筋肉が引き締まり、顔全体が小さく見える効果が期待されます。
当院では美容鍼を得意としているスタッフが多数在籍しております!
是非お気軽にご相談くださいませ! -
大人の熱中症対策! 皆さんこんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!!
まだまだ暑い日が続いておりますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
熱中症対策は出来ていますでしょうか?
今回はそんな熱中症対策をご紹介します!
まず、朝起きたときにコップ一杯の水約200mlを飲み夜のうちに汗や呼吸で出ていってしまった水分を補給しましょう!
そして、朝食には味噌汁が一番です!
ミネラルが豊富で胃にやさしく温かいものなので過度に刺激もしないのでオススメです!
汗をかいたらスポドリではなく、酸味のあるものを取りましょう!
梅干しと水、塩レモンなどがいいでしょう
いざというときは経口補水液を飲みましょう!
なんか身体が怪しいぞと思ったら一口飲んでみましょう。
スポドリは糖質が多く、むくみや逆に喉が渇いてしまったりなど逆効果になってしまう事も・・・
身体がほてっているなと思ったら頭と首を冷やすべし!
機能は落とさず、体温を効果的に落としてくれるのでオススメです!
足がつってしまうのも熱中症の初期症状になります
最近よくあしがつる、手が震えると思ったら熱中症のサインでもあるので早めに経口補水液などで対策しましょう!
また、いつも以上にマッサージをしたりストレッチをしてこまめに水分+塩分+酸味をチャージしましょう!
まとめると・・
①水分補給は体重をみる
②朝は味噌汁
③首と頭を冷やすべし
④エアコンを活用すべし
⑤足がつったら要注意
⑥お守りに経口補水液
です!
当院でも対策方法をお教えしていますのでご連絡お待ちしております! -
睡眠障害の原因、お勧めのツボ こんにちは!
りゅう鍼灸整骨院です!
本日は睡眠障害について東洋医学的観点からお話ししようと思います!
睡眠障害とは、睡眠の異常によって日常生活への支障や、QOLの低下が起こる状態である。
睡眠障害は不眠だけではなく、覚醒時の過剰な眠気、睡眠中に生じる異常な運動や行動、睡眠リズムの乱れなどがある。
東洋医学
失眠:睡眠が不足するもの
不眠と同じ意味をさします。
嗜眠:昼夜とやず眠くなるもの
心神がかき乱される(心神擾乱)、心神や髄海が十分に滋養されない(心神失養)などにより睡眠上が引き起こさせる。
睡眠中の神(脳)は陰や血による滋養を受けている(寧静、滋潤作用)
この作用が乱れてしまうと、睡眠に問題が生じてしまいます。
内熱が発生している場合...
熱や陽気が強いと覚醒してしまう。
特に入眠障害が顕著となってしまいます。
血虚が発生している場合...
血が不足すると、寧静作用が失われ中途覚醒してしまう。
睡眠障害に対して効果が期待されるツボ(経穴)は、リラックスを促し、精神を安定させる作用を持つものが多いです。以下に、睡眠の質を改善するためによく用いられるツボを紹介します。
1. 百会(ひゃくえ)
• 位置: 頭のてっぺん、両耳の上端を結んだ線と、顔の正中線が交わるところにあります。
• 効果: 精神を安定させ、リラックスを促す効果があるため、入眠を助けることが期待されます。また、気の流れを整え、頭痛やめまいにも効果的です。
2. 神門(しんもん)
• 位置: 手首の内側、手のひら側のしわの小指側にあるくぼみです。
• 効果: 不安や緊張を和らげ、心を落ち着かせる効果があります。これにより、寝つきが良くなることが期待されます。
3. 安眠(あんみん)
• 位置: 耳の後ろ、乳様突起の下端と下顎の間のくぼみにあります。
• 効果: その名の通り、睡眠を改善するために用いられるツボです。不眠症やストレスによる睡眠障害に効果的とされています。
4. 内関(ないかん)
• 位置: 手首の内側、手のひら側で、手首のしわから指3本分上の中央にあります。
• 効果: 精神を安定させ、リラックスを促します。また、吐き気や動悸を和らげる効果もあり、心身のバランスを整えます。
5. 太衝(たいしょう)
• 位置: 足の甲で、親指と第二指の骨が交わる部分の少し後ろにあります。
• 効果: ストレスを軽減し、精神的な緊張を緩和する効果があるため、寝つきが悪いときに役立ちます。肝気の流れを良くする作用もあり、全身のリラックスを促進します。
6. 三陰交(さんいんこう)
• 位置: 内くるぶしの上約4寸(約10cm)の脛骨内側の際にあります。
• 効果: ホルモンバランスの調整や、血の巡りを良くする効果があります。特に、女性のホルモンバランスの乱れによる不眠や、冷え性による睡眠障害に効果的です。
7. 足三里(あしさんり)
• 位置: 膝の外側、脛骨の前面の縁から外側に指4本分下がったところにあります。
• 効果: 気血の巡りを良くし、胃腸の調子を整えるとともに、全身のリラックスを促す効果があります。
内熱に対する経穴
内熱の症状(例えば、口渇、のぼせ、顔面紅潮、便秘、口内炎など)に対応するために、以下の経穴が選ばれることがあります。
1. 曲池(きょくち):
• 位置: 肘を曲げたときにできるシワの外側端。
• 効果: 体内の余分な熱を取り除く効果があるとされます。
2. 合谷(ごうこく):
• 位置: 手の甲で、親指と人差し指の骨が交わる部分。
• 効果: 全身の熱を鎮める効果があり、特に頭痛や目の充血、顔面紅潮に有効です。
3. 大椎(だいつい):
• 位置: 首の後ろの最も大きな突起のある骨(第七頸椎)の下のくぼみ。
• 効果: 体内の熱を散らす作用があり、発熱やのぼせに使用されます。
4. 内庭(ないてい):
• 位置: 足の甲、第二・第三指の間のくぼみ。
• 効果: 胃腸の熱を鎮め、消化器系の不調を改善します。
血虚に対する経穴
血虚の症状(例えば、顔色不良、めまい、不眠、冷え性、疲労感など)を改善するために、以下の経穴がよく使用されます。
1. 三陰交(さんいんこう):
• 位置: 内くるぶしの上約4寸(約10cm)の脛骨内側の際。
• 効果: 血を補い、月経不順や不眠などの血虚に関連する症状を改善します。
2. 足三里(あしさんり):
• 位置: 膝の外側下、脛骨の前面の縁から外側に指4本分のところ。
• 効果: 全身の気血を補い、消化機能を改善して血虚を緩和します。
3. 膈兪(かくゆ):
• 位置: 背中の第7胸椎棘突起の下、脊柱の両側指1.5寸のところ。
• 効果: 血を補い、特に貧血や疲労感に有効です。
4. 肝兪(かんゆ):
• 位置: 第9胸椎棘突起の下、脊柱の両側指1.5寸のところ。
• 効果: 血を補う効果があり、特に目の疲れや肝血虚に有効です。
睡眠障害でお悩みの方は是非、今のツボを10秒くらい推してみてください! -
痺れの原因 こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
今ご覧の皆様はどんな症状にお困りでしょうか??
この記事では足の痺れの原因とセルフケア方法を説明していきます!
『セルフケアって大切??』
セルフケアはわからないし、治療してるから大丈夫と思う方は多いと思います。
ですが1日24時間で治療を受けているのは1時間、23時間は治療を受けていません。この23時間でセルフケアや姿勢をどれだけ意識できるかで治療の意味や効果、改善の早さが変わってきます!!
『坐骨神経痛は2種類ある??』
さて本題の足の痺れですが、足の痺れとして代表的な坐骨神経痛は2種類ある事はご存知でしょうか?
・1つ目は臀部の筋肉が固くなり、神経を圧迫してしまい、痺れが出ている。
・2つ目は腰の歪みなどにより神経を圧迫し、痺れが出ている。
この2種類があり、痺れが出ている部分に注目しがちですが、実は腰が原因なんて事が沢山あるんです!
〜セルフケア方法〜
セルフケアってどんな事をしたらいいかわからないですよね、、、
坐骨神経痛は筋肉が神経を圧迫している事が多いので、固く圧迫している筋肉を緩めてあげる事が大切です!
下記のストレッチや対処法をぜひ実践してみてください!
・湯船にしっかりと浸かる
40度に15〜20分しっかりと浸かりましょう!
・臀部のストレッチ
臀部のストレッチは椅子で簡単に行えます!
片方の外くるぶしを膝の上に乗せ、上半身を前に倒します!
臀部が伸びている事を感じながらやりましょう!
この2つがメインとなるセルフケアになります!
このセルフケアは痺れや痛みが出た時の対処法になります。
治ってもまた症状が出てしまう事があり、矯正、鍼、マッサージなどでしっかりと治療すると共にセルフケアをする事で根本改善に繋がりますのでお気軽にご連絡ください! -
暑さ続いていますね・・・ こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
最近うだるような暑さが続いていますね、
皆さんは熱中症対策はされていますでしょうか?
私は水分を十分に摂取して沢山汗をかくようにしています。
そんな熱中症になりやすい方を今回紹介したいと思います。
それは、舌の先の方がツブツブしている方です!
この方は身体に熱がこもりやすくのぼせやすい体質になります。
そんな体質を二つのツボで改善しちゃいましょう!
まずは手のひら側小指と薬指の付け根にある「少府」です!
力を抜いて反対の手で包み込むように親指でぎゅーって押してあげましょう!
慣れてきたら骨と骨の間から少府に向かって流してあげる様にスライド!
続いてはこちらもまた手のひら側
手首のしわの小指側の端っこから少し肘寄りにある「陰げき」というツボです!
こちらも反対と親指で押してあげたり、押しながら手をグーパーしてあげましょう!
汗をかいたらこまめに汗を拭きとってあげましょう。
様々なツボを用いて今年の夏も乗り越えて行きましょう! -
梅雨ですね。。。 こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
まだまだジメジメした日が続いていますね、、
皆さんはいかがお過ごしですか?
体に不調が出たりしていませんか?
梅雨の季節は湿度が高く、身体の中に水分が溜まりやすくまた、外にも排出されないので停滞してしまいます。
ではどうすればいいのかと言いますと、
つま先立ちを繰り返してふくらはぎを動かしてポンプ作用を促し、巡らせることでろ過して外へ排出させます。
要するに運動しましょうという事になります(笑)
それでも改善しない方は当院でぜひ治療を受けに来てください‼
違う理由で水分が溜まっている可能性があるかもしれません。
ご連絡お待ちしております。 -
必要な水分 こんにちは、笹塚のりゅう鍼灸整骨院です!
暑い日が続いたり、1日中雨が続いたりと嫌な天気が多いですね…。
体の調子をしっかりと整えて、6月最後の週を元気に過ごして行きましょう!
真夏の時期になると外にいるだけで汗がダラダラと流れてきますね。
汗が流れると体内の水分量が減るのは勿論ですが、
実は汗をかいていなくても体から水分は失われているのです。
水分喪失にはいくつかの種類があります
1不感蒸泄によるもの
水分の喪失というと暑さによる発汗がイメージしやすいですが、
日常生活を送るうえで自然に失われている水分というのもあります。
これを不感蒸泄(ふかんじょうせつ)と呼びます。
人は知らず知らずのうちに皮膚や気道の粘膜から水分を失っています。
個人差はもちろんありますが1日に平均して皮膚からは500~700mL、l呼気(吐く息)で150~450mの水分が排出されています。
3尿による排泄
多すぎる多尿や少ない乏尿などありますが、
成人の平均1日尿量は約1000mlから2000mlといわれています。
このように、人は意識していないうちに多くのの水分を失っています。
水分が少ないと筋肉がかたくなることによる肩こり腰痛、頭痛や便秘、むくみの原因ともなります。
逆に十分な水分量があると血液がサラサラになったり代謝があがるなどなど健康上のメリットがあります。
積極的に水分を摂っていきましょう!
※1日に6リットルといった過剰な水分摂取は低ナトリウム血症などの症状を引き起こすので、ご注意ください。
お身体の不調やお悩みは、ぜひ笹塚のりゅう鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください! -
久しぶりの運動!! みなさん、こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!!
最近、暑くなりはじめ外に出るだけでも汗が噴き出てきますね、、
そして、運動不足を感じています…
みなさんはいかがですか?
自分はとっても運動不足を感じているため、久しぶりに縄跳びをやりました!
縄跳びは場所もそんなに必要としないため、気軽にできてかつ、全身の筋肉を使うため効率よく身体を動かす事ができます!!
着地の際に、足先から強い衝撃が加わるため骨にとっても脳にとっても良い刺激を与えることができるのです。
また、まっすぐに跳ばないといけないため体幹も鍛えられて縄跳びの運動強度はランニングより高いとも言われています。
1日10分間やるだけでもたくさん汗をかけますし体全体がスッキリしますよ!!
普段から運動する習慣がない人でも簡単に始められるのでオススメです! -
6月30周年キャンペーン!! こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
遅くなりましたが、6月はりゅう鍼灸整骨院始まって30周年を迎えました!
皆様ありがとうございます!
そこで、皆様へ感謝の30周年キャンペーンを始めさせて頂きました!
内容はポイントチャージ時更にポイントを付与させていただきます!
最大5500円上乗せで付与させていただきます!
このポイントで美顔鍼やオイルマッサージなど自分の美や健康にご活用下さい!
これからもりゅう鍼灸整骨院をよろしくお願いいたします! -
梅雨対策!血流改善のツボ! こんにちは!りゅう鍼灸整骨院です!
今日で5月が終わり梅雨の時期が近づいてきました。
この時期は湿度が高くジメジメしていて雨の日は肌寒く感じることがあると思います。その結果身体の中の水分量が多くなり浮腫が現れ血流が悪くなってしまいます。
そこで今回は「血流改善のツボ」をお教えします!
1つ目、「血海」
大腿前内側にあり、膝の内側でお皿の上(指3本分)にあります。
血海はその名の通り血の海といい血流に関わっているツボです。
血の滞りを解消し、血行を促進させることから月経不順や月経痛などの症状にも非常に効果的です
2つ目、「三陰交」
うちくるぶし(内果)上(指4本分)で筋肉と骨の境目にあります。
三陰交は月経や妊娠と深く関連しているツボで、生理痛や不妊など女性特有の症状に効果が高いとされています。血流が促進されることで冷え性を解消する働きも。
3つ目、「合谷」
手の親指と人差し指の骨が交わったところにあるくぼみにあります。
合谷を刺激することで、血行促進作用により眼精疲労や肩こりなどさまざまな症状を改善する効果があります。
今回紹介したツボをマッサージするのはもちろん、鍼やお灸で刺激を与えるとより効果を感じることができます!
血流の悪さが気になっている方やその他お悩みがあればご気軽にご相談ください!