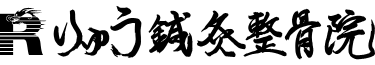鍼灸の歴史と現代の立ち位置

日本で長い歴史を持つ鍼灸療法ですが、その起源や発展については、あまり知られていないかもしれません。鍼灸を含む東洋医学は西洋医学と度々比較されますが、現代では両者の特長を活かした統合医療が注目されています。
本コラムでは、鍼灸の歴史的背景と現代医療における位置づけについてご紹介いたします。
鍼灸の歴史について
鍼灸の発祥は中国で、約2000年以上の歴史があります。
日本には6世紀頃に伝来し律令制度が整うに従い、医療職として鍼灸を行うようになります。鍼灸は東洋医学の主流として発展し、日本でも明治初期まで医療の中心として用いられました。しかし、同時期に西洋医学が伝わると、鍼灸を始めとする東洋医学は衰退します。
戦後、GHQに鍼灸を禁止しようとする動きがありましたが、鍼灸存続運動によるGHQへの陳情が受理され、「あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律」の原型となる法律が昭和22年に制定されます。
世界に広まる鍼灸
1979年、世界保健機関(WHO)が鍼灸治療の適応疾患を発表し、鍼灸医学は国際的に認知され始めました。1989年には、鍼灸の専門用語である「経絡」や「経穴」の名称がジュネーブ国際会議で認められ、さらに2008年には経穴の国際標準化が実現しました。
東洋医学の中心である鍼灸治療が世界的にも有効と認められたことで、自分に合った治療法を選択できるようになりました。
東洋医学と西洋医学には、診断や治療アプローチに根本的な違いがあります。
例えば診断に関して、東洋医学は「気」の流れが健康状態に大きな影響を与えると考えられ、気の乱れが病気や不調の原因とされています。患者さまの身体に直接触れて全身を観察し、不調の根本原因を探るのが特徴です。
対して、西洋医学でも触診は行われますが、画像診断や血液検査など、客観的なデータを用いた診断が中心となります。さらに、治療法についての考え方でも東洋医学と西洋医学では異なります。東洋医学は、患者さまそれぞれの体格・体質を考慮して個別に治療法を考えるのに対し、西洋医学では「ある症状にはこの薬を使用する」など、標準化された治療法を用いるのが一般的です。
近年では世界中で鍼灸医学の研究が進んでおり、東洋医学と西洋医学、双方の利点を活かした「統合医療」にも注目が集まっています。今後はそれぞれの強みを融合させることで、より効果的な治療が期待できます。
記事監修|りゅう鍼灸整骨院 院長 土谷禎之

■経歴
- 両国柔整鍼灸専門学校 卒業
- 神田第一接骨院 院長
- ふれあい鍼灸整骨院 院長
- りゅう鍼灸整骨院 院長
■得意な治療
- 外傷から慢性疾患の患者様それぞれの
症状に合わせた施術・アドバイス